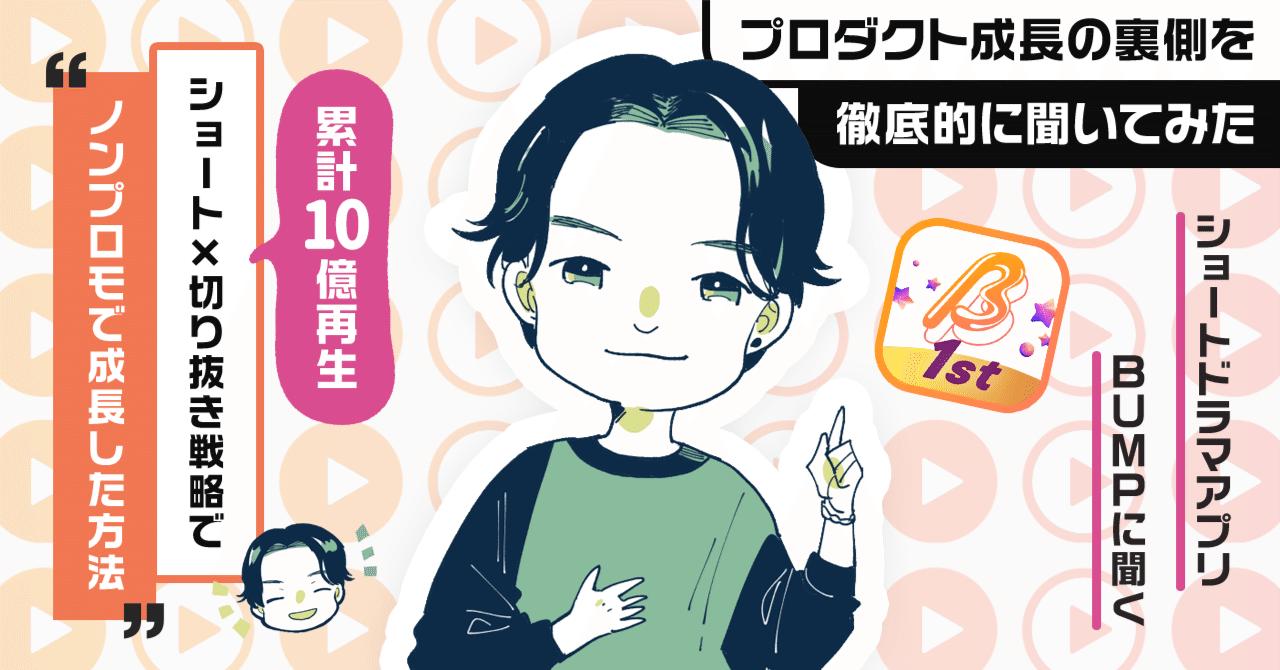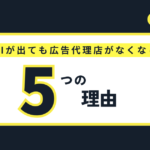コンテンツ消費の形態は常に変化しています。
テレビからインターネット、そしてスマートフォンへと移り変わる中で、コンテンツの「尺」も大きく変化してきました。
かつて30分〜2時間が基本だったドラマが、わずか3分程度で視聴できる「ショートドラマ」として新たな地位を確立しつつあります。この記事では2020年から2025年にかけて急成長を遂げるこのショートドラマが、次世代のマーケティング媒体として注目を集めている理由を探り、どのように活かしていけるのか予測します。
消費者の時間価値観を変えたショートドラマの台頭
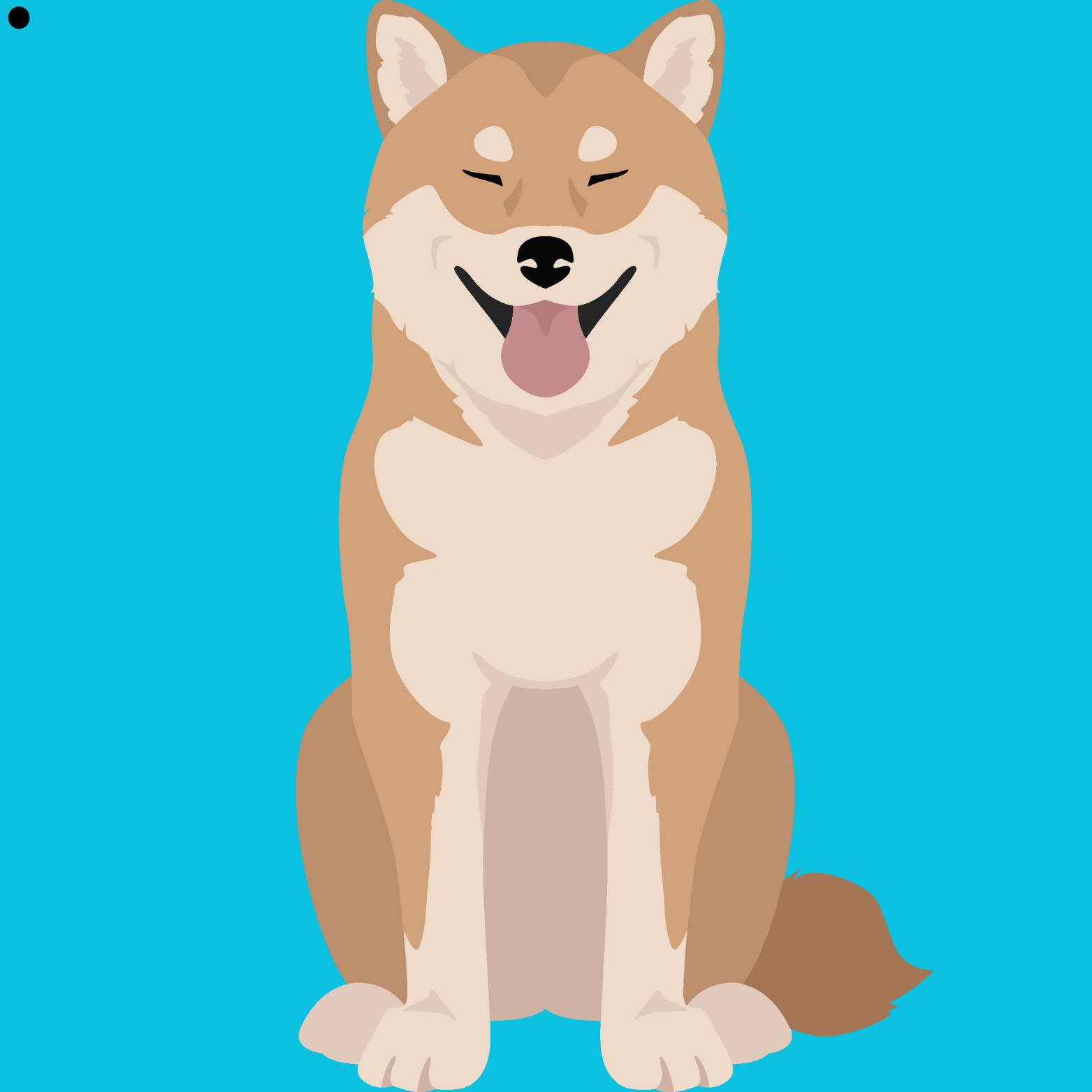
「あっという間に終わる」ことが強みになる時代が到来しました。
スマホの普及により、いつでもどこでもコンテンツを消費できるようになった現代の若者たちは、限られた時間の中で効率よく満足感を得られるコンテンツを求めています。
特にZ世代はタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向が強く、少ない時間投資で高い満足感を得られるコンテンツへの嗜好が顕著です。
このような背景から生まれたのが「ショートドラマ」です。1話あたり3分程度という超短尺ながら、従来のドラマと同様の世界観や感情移入を実現させるこの新しいコンテンツ形式は、若年層を中心に急速に支持を拡大しています。先駆者としてマンガアプリが「1分で読める」というモデルでヒットを飛ばした後、その手法をドラマコンテンツに応用したのがショートドラマの始まりだったとも言えます。
BUMPが切り開いたショートドラマのエコシステム
2022年12月、emole株式会社がリリースしたショートドラマ配信アプリ「BUMP」は、この新しいコンテンツ市場に革命をもたらしました。当初は広告を一切打たずにサービスを展開し、わずか2年の間に累計85万ダウンロードを突破。ユーザーの75%が10代から20代のZ世代で構成されています。
運営するemoleの代表取締役CEO澤村直道氏によれば、BUMPは「テレビドラマの面白さのままに、1話の尺を短くできたら面白いのではないか」という着想から生まれたそうです。しかし、サービス立ち上げ当初はコンテンツもプロダクトも何もない状態からのスタートだったんです。制作に関わる人材集めも困難を極め、毎日のようにDMでの依頼が続いたとか。
転機となったのは、実績のある監督の参画だったようです。澤村氏は「監督が決まったことで、出演者やスタッフを集められるようになった」と振り返っています。監督の影響力は大きく、芸能事務所も「この監督なら出ます」となり、カメラマンも「この監督なら付き合うよ」と応じてくれるようになったとのことです。
マネタイズの壁を突破した従量課金制
ショートドラマは2020年ごろから動画SNSに投稿され、YouTube や TikTok で高い人気を集めていましたが、その最大の課題はマネタイズの難しさでした。
例えば、YouTubeで100万再生を達成したとしても、広告単価は0.1〜0.5円といわれる中、収益は数十万円程度にしかならず、数百万、時には1000万円前後ともいわれる制作費と見合わなかったのです。
BUMPが採用したのは、マンガアプリを参考にした従量課金制です。
基本的に1話ずつ67円(税込み)で「話売り」する仕組みで、3話まで無料で視聴でき、それ以降はコインに課金して視聴するモデルを構築しました。このモデルが機能するかどうかは「ユーザーが課金してくれるか」にかかっていたので、リリース時には恋愛・アクション・不倫など、意図的にジャンルを分散させた6作品を公開し、相性の良いジャンルを探ったそうです。
結果として『今日も浮つく、あなたは燃える』という不倫をテーマにした作品がヒットし、ショートドラマの課金モデルが「制作費の何倍もの収益を生み出せること」を証明しました。特に「インモラル系」と呼ばれる、不倫などの背徳感を感じさせるジャンルはショートドラマと相性が良いことが判明したんです。これにより、若年層ユーザーがショートドラマに課金する可能性が確認され、新作の制作を進める原動力となりました。
ショートドラマ制作の新たな法則
ショートドラマは従来のドラマとは異なる制作手法が求められます。特に注目すべきは「頭サビ」の手法です。音楽でいえば冒頭からサビを持ってくるように、ドラマでも冒頭から物語の柱となる衝撃的なシーンを流し、視聴者の関心を一気に引きつけます。
また各話の最後には必ず「クリフハンガー」と呼ばれる、続きを期待させるような場面を挿入し、次の話も見ずにはいられない状況を作り出します。こうしてショートドラマを最終話まで飽きさせないようにし、全話の視聴へと誘導するわけです。
澤村氏によれば、ヒット作品の共通点は「最終話まで見てくれる人が多いこと」だそうです。これは「1話の視聴者の母数」と「継続視聴率の高さ」の掛け算で決まるとのこと。特に重要なのは1話の出来栄えで、冒頭30秒に感情を揺さぶるフックとなるシーンを入れ、その作品が「最終的にどこに向かっていく話なのか」を明確に伝えることが求められます。
例えば「桃太郎」のショートドラマを作るなら、従来のように「昔々…」からゆっくり始めるのではなく、いきなり鬼に爺さん婆さんが襲われるシーンから入るほうが引きは生まれやすいんです。これは「鬼滅の刃」の1話目の構成に似ていて、鬼を倒す動機づけと主人公を応援したくなる理由を短時間で提示し、次への引きで終わらせる手法なのです。
切り抜き戦略が牽引する爆発的成長
BUMPの急成長の背景には「切り抜き動画」戦略があるんです。印象的なシーンの「切り抜き」をSNSにアップすることで、月間数千万再生を達成し、アプリへの流入を促進しています。新作ドラマが公開されると、そのハイライトシーンを切り抜いてSNSに投稿し、それを視聴したユーザーがアプリをダウンロードするという循環が生まれています。
注目すべきは、同じようにバズった切り抜き動画でも、アプリのダウンロードにつながるコンバージョン率(CVR)には差があるということです。分析の結果、CVRが高い動画の特徴は「ストーリーの続きが気になるもの」であることが分かったそうです。視聴後に「アプリをダウンロードする動機」が生まれるからなんですね。
このため、脚本段階から「各話にどれだけバズるシーンが作れるか」も意識され、1つの作品から多数の切り抜きが生まれるよう設計されているとのこと。BUMPでは「バズレベルシート」という評価システムを用い、脚本の中に「バズりそうな切り抜きが作れそうか」を評価する仕組みも導入しているようです。
SNS特性を活かした切り抜き動画の最適化
ショート動画は「最初の1秒」で視聴するか離脱するかが決まるため、テロップを動画の上下に入れて「最初の1秒の情報量」を増やす工夫がされています。テロップで「シーンの状況」を伝えることで視覚的なアイキャッチとなり、視聴の継続率が高まるのです。最初の1秒でセリフだけで伝えられる情報量は限られているため、テロップを使って視覚的な情報量を補完しています。
さらに、SNSプラットフォームごとに動画を出し分ける戦略も採用されています。同じショート動画でも、SNSによって「ウケるネタ」が異なるからです。例えば、Instagramでは「共感を呼ぶあるあるネタ」が人気を集めるため、テロップにも共感度の高そうな文言を入れるという工夫がされているそうです。
興味深いのは、切り抜きの再生数はSNSプラットフォームによって大きく異なるわけではなく、動画のコンテンツによってバラバラということです。これは、どのSNSも等しく重要であり、それぞれの特性を理解した上で最適化を図る必要があることを示しています。
クリエイターエコノミーの新たな展開
BUMPの革新的な点は、制作会社やクリエイター、出演する俳優に着実に収益が回る仕組みを整えたことです。収益モデルはBUMPに掲載した作品から生まれた収益をクリエイターと分け合うレベニューシェアモデルで、作品がヒットすればするほど、それに見合った報酬を得られるというものです。
実際に、これまでで最もヒットしたBUMP配信のドラマは、制作費の3倍以上の収益を達成しているそうです。作品あたりの収益のベースラインも伸びており、制作費の回収が見込める作品も増えているとのこと。これにより、制作会社やクリエイターがショートドラマの制作で着実に収益を上げ、その資金で次の作品を制作するという好循環が生まれつつあるのです。
マーケティング媒体としてのショートドラマの可能性
ショートドラマがビジネスとして成立し始めたことで、マーケティング媒体としての可能性も広がりつつあります。特に注目すべきは以下の点です。
- Z世代へのリーチ力の高さ
- エンゲージメントの深さ
- バイラル拡散の容易さ
第一に、Z世代へのリーチ力の高さです。BUMPのユーザーは10〜20代が約75%(うち20代が56%)を占めており、若年層へのアプローチに悩む企業にとって貴重な接点となり得えます。従来のテレビCMでは届きにくかったZ世代に対し、彼らの嗜好に合わせたコンテンツを通じてブランドメッセージを伝えることが可能になるわけです。
第二に、エンゲージメントの深さです。ショートドラマは視聴者の感情を揺さぶり、強い印象を残すコンテンツとして機能します。特に「継続視聴率の高さ」はマーケティング担当者にとって魅力的な特性であり、ブランドストーリーをシリーズで展開するといった新たな可能性を秘めているんです。
第三に、バイラル拡散の容易さです。切り抜き動画戦略が示すように、ショートドラマは自然と拡散される要素を内包しているんですよ。インパクトのあるシーンや共感を呼ぶ展開を盛り込むことで、視聴者自身が周囲にシェアしたくなるようなコンテンツを設計しやすいんです。
2025年、ショートドラママーケティングの展望
コンテンツ消費の変化と技術の進化を背景に、2025年に向けてショートドラマはマーケティング媒体としての地位を確立していくでしょう。特に以下の動向が予測されます。
まず、ブランド主導のオリジナルショートドラマの増加が考えられます。製品やサービスを直接的に宣伝するのではなく、ブランドの世界観を表現するショートドラマを制作・配信する企業が増えると予想されます。これは従来のブランデッドコンテンツの発展形であり、より自然な形でターゲット層の共感を得る手法として注目されているんです。
次に、インフルエンサーとの連携強化も進むでしょう。ショートドラマの出演者として人気インフルエンサーを起用することで、そのファン層を取り込むアプローチが活発化すると考えられます。特にZ世代に影響力を持つTikTokerや YouTuber の出演は、作品の拡散力を大幅に高める可能性があるのです。
さらに、データ活用による最適化の進展も見込まれます。BUMPが「フックレベルシート」や「バズレベルシート」を活用しているように、視聴者の反応データを分析し、より効果的なストーリー展開や演出を導き出す手法が洗練されていくでしょう。マーケティング担当者にとっても、ターゲット層の反応を可視化できるツールとしての価値が高まるのです。
マーケティング手法としてのショートドラマの課題と可能性
ショートドラマが新たなマーケティング媒体として定着するためには、いくつかの課題も存在します。制作コストと効果測定の難しさ、専門的なノウハウの不足などが挙げられます。一作品の制作費が数百万円から1000万円前後という点は、多くの企業にとって大きな投資であり、その費用対効果を明確に示す指標の確立が求められます。。
一方で、従来の広告手法では捉えきれなかった層へのリーチや、深い感情的つながりの構築という点で、ショートドラマは他のマーケティング手法にない強みを持っています。特にブランドストーリーの伝達や価値観の共有といった、深いレベルでのブランディングに適したメディアといえるでしょう。
2025年に向けて、マーケティング担当者はショートドラマという新たな選択肢をPF(ポートフォリオ)に加え、状況に応じて最適なアプローチを選択できるようになることが重要になりそうです。若年層との接点を求める企業や、より感情に訴えかけるブランディングを目指す企業にとって、ショートドラマは確実に検討すべきチャネルとなるでしょう。
まとめ:新時代のマーケティング媒体としてのショートドラマ
コンテンツ消費の形態が変化し続ける中で、ショートドラマは時代のニーズに応えた新たなメディアとして急速に成長しています。BUMPに代表される成功事例は、適切なマネタイズモデルとコンテンツ設計により、持続可能なエコシステムを構築できることを証明しました。
Z世代を中心とした新しい消費者層の獲得に悩むマーケティング担当者にとって、ショートドラマは単なるトレンドではなく、中長期的な戦略に組み込むべき重要な選択肢となります。2025年、マーケティングのランドスケープにおいて、ショートドラマが確固たる地位を築いていることは間違いないです。
今後、この分野に参入する企業や制作者には、ショートドラマの特性を理解し、その魅力を最大限に引き出すクリエイティブ力が求められます。「3分」という短い時間の中で視聴者の心を掴み、行動を促すストーリーテリングの技術は、デジタル時代のマーケティングに不可欠なスキルとなるでしょう。