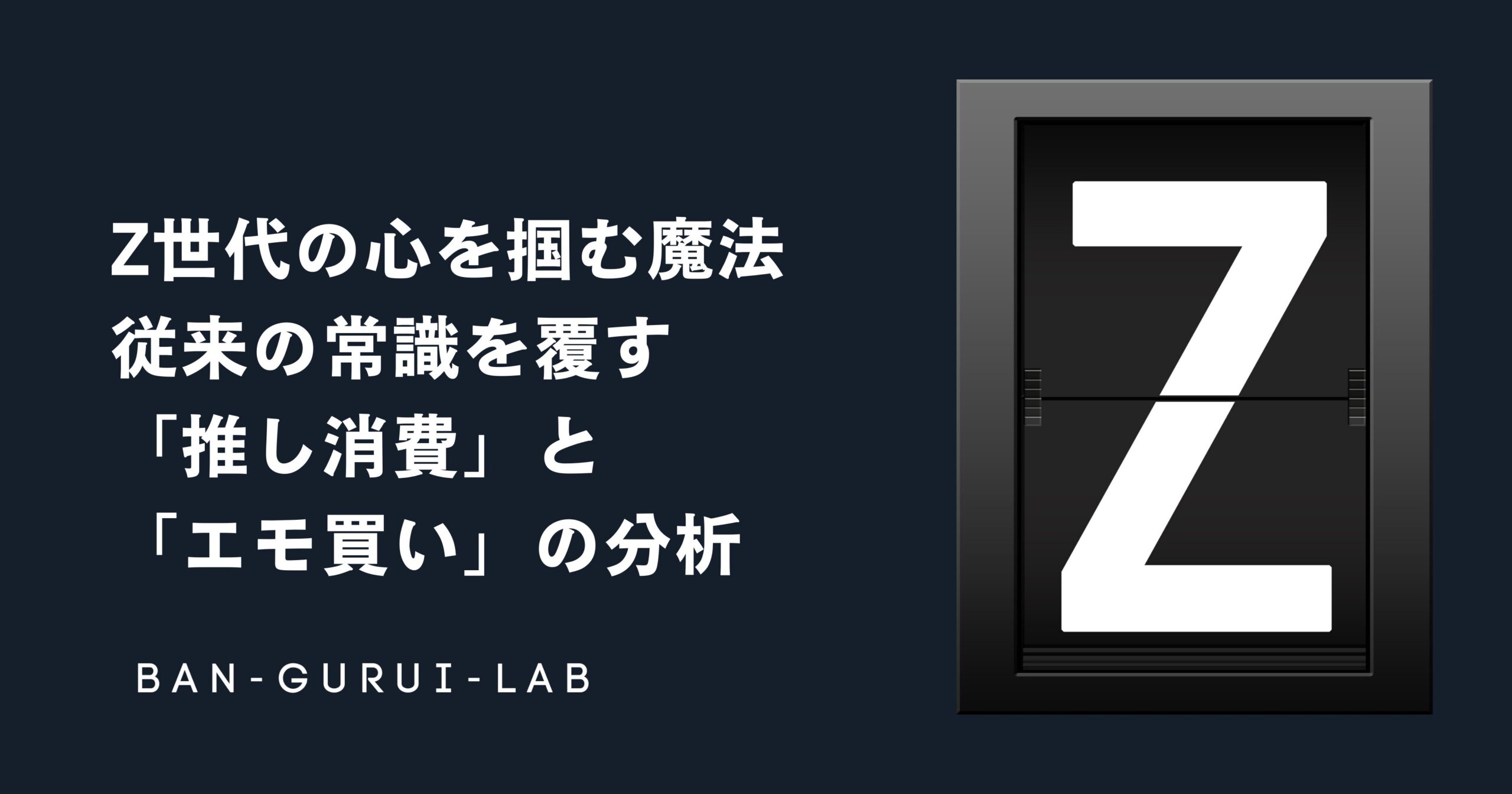現代の若者、いわゆる「Z世代」の消費行動が、これまでのマーケティング理論では説明しきれない、興味深い変化を見せています。生まれたときからインターネットやSNSが当たり前のように存在し、リーマンショックや震災といった社会的な出来事も経験してきた彼らは、上の世代とは異なる価値観を持ち、独特の消費スタイルを築き上げています。一見すると非合理的に見える彼らの選択の裏には、一体何があるのでしょうか?
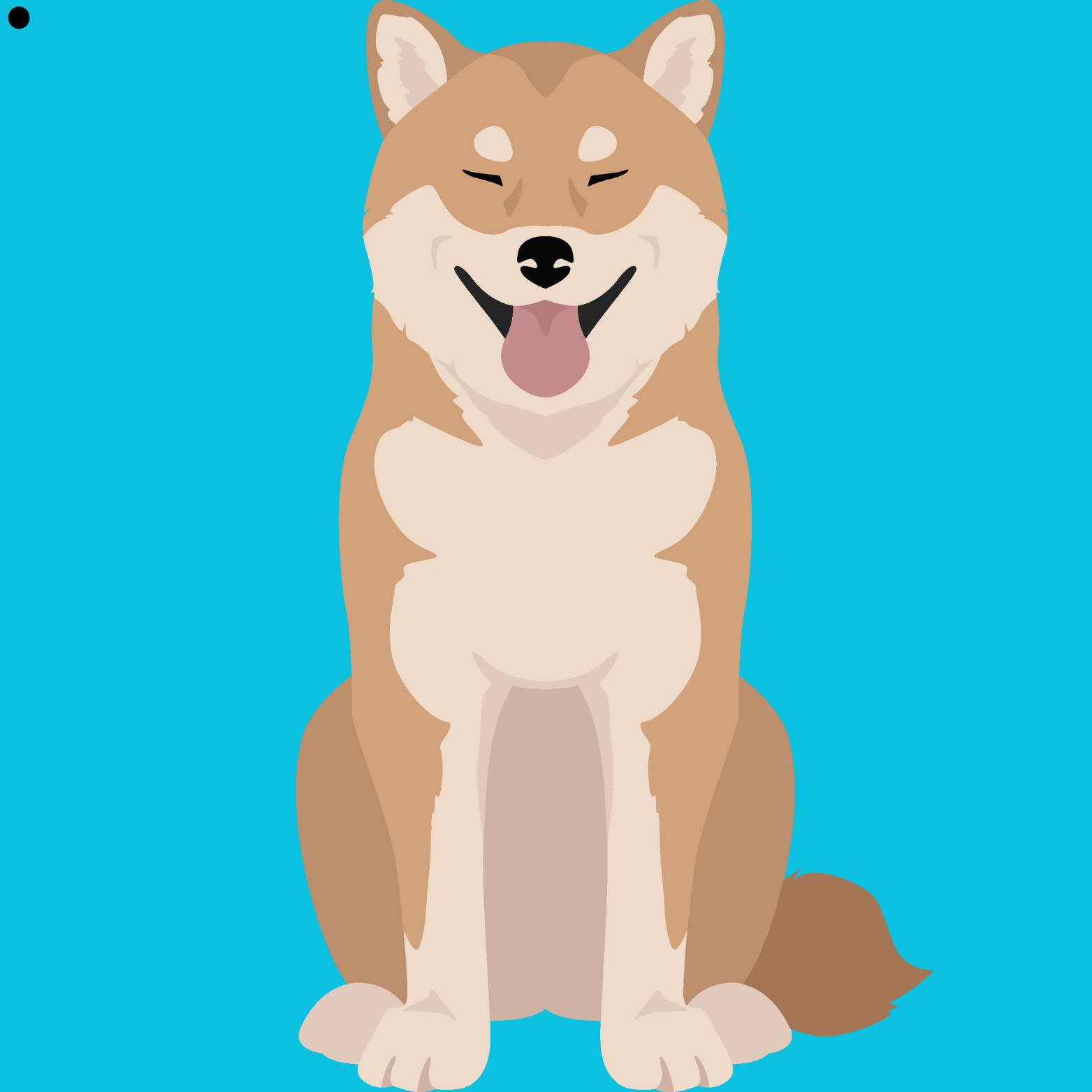
その答えを探る鍵となるのが、「推し消費」と「エモ買い」という、感情を軸にした新しい消費の形です。
かつて、消費者の購買行動は、注意(Attention)、興味(Interest)、欲求(Desire)、記憶(Memory)、行動(Action)の頭文字をとった「AIDMA」や、インターネット時代の行動を加味した「AISAS」といったモデルで説明されてきました。これらは、消費者が商品やサービスを認知し、段階的に関心を深め、最終的に購買に至るという、比較的直線的なプロセスを想定していました。
しかし、情報が瞬時に、そして膨大に行き交う現代において、特にSNSを駆使するZ世代の行動は、もはやこれらのモデルだけでは捉えきれません。
SNSでの共感が購買を後押ししたり、特定の商品情報を探すことなく偶発的な出会いから購入に至る「パルス型消費」と呼ばれる行動が見られたりと、そのプロセスはより複雑で、感情的な側面が色濃く影響しています。
Z世代の消費者行動の象徴「推し消費」
こうしたZ世代の消費行動を象徴するのが、「推し消費」です。これは、自身が熱烈に応援するアイドル、俳優、キャラクター、あるいは特定のコンテンツなどを「推し」と呼び、その「推し」を支えたい、貢献したいという強い気持ちから生まれる消費活動を指します。
「応援消費」や「ヒト消費」とも呼ばれ、その市場規模は8000億円を超えるとも推計されるほど、大きな潮流となっています。彼らは「推し」のグッズを購入したり、イベントに参加したりするだけでなく、SNS上で「推し」の魅力を積極的に発信し、ファン同士で繋がり、一体感を深めていきます。
ここで重要なのは、彼らの行動原理が、単に「そのモノが欲しい」という所有欲だけではない点です。「推し」の活動資金になるなら、より良いパフォーマンスに繋がるなら、という貢献意欲が、時に高額な出費をも厭わない強い動機となっています。
これは、従来の費用対効果や機能性といった合理的な判断基準とは異なる、極めて感情的な価値基準が働いていることを示しています。
多くの企業もこの熱量に注目し、例えばサンリオはキャラクターのファン(推し)に向けた多様なグッズ展開やイベントを実施し、ロクシタンは製品と「推し」を結びつけるキャンペーンを展開するなど、ファンの応援したい気持ちに応えるマーケティングに取り組んでいます。
もう一つのZ世代の消費者行動の象徴「エモ買い」
そしてもう一つ、Z世代の消費を理解する上で欠かせないキーワードが「エモ買い」、すなわち「エモ消費」です。
これは、商品やサービスの機能的な価値、いわゆるスペックや価格といった合理的な要素だけでなく、それを通じて得られる感情的な価値、つまり「エモさ」を重視する購買行動を指します。「エモい」という言葉自体が示すように、それは懐かしさ(ノスタルジー)、可愛らしさ、切なさ、感動、共感といった、一言では言い表しにくい、心の琴線に触れるような感覚です。
例えば、サントリーが発売した「BAR Pomum(バー・ポームム)」は、どこか懐かしさを感じさせるパッケージデザインと、ゆったりとした時間を演出するコンセプトが若年層の共感を呼びました。
また、カンロの「夏夜のカケラCANDY」は、夏の終わりの切なさを表現したコンセプトやパッケージが「エモい」と話題になりました。
Z世代は、デジタルネイティブとして効率性を重視し、「コスパ(コストパフォーマンス)」や「タイパ(タイムパフォーマンス)」に敏感な側面を持つ一方で、このように自身の感情を満たし、心を豊かにしてくれると感じるものに対しては、進んで対価を支払う傾向があるのです。これは、単なるモノの所有や便利な機能だけでは満たされない、深い精神的な満足感を求めていることの表れと言えるでしょう。
なぜZ世代にとって「推し」や「エモさ」がこれほどまでに重要なのか。
では、なぜZ世代にとって「推し」や「エモさ」がこれほどまでに重要なのでしょうか。
「推し消費」と「エモ買い」に共通して見られるのは、「共感」と「自己表現」への強い欲求です。彼らは、自分が何に価値を感じ、何に心を動かされるかということを非常に大切にしており、商品やサービスを選ぶ行為そのものが、自身のアイデンティティや価値観を表現する手段となっています。
そして、その価値観を共有できる他者との繋がりに喜びを見出します。SNSは、単に情報を集めたり発信したりするだけのツールではありません。同じ「推し」を応援する仲間と繋がったり、「エモい」と感じた体験を共有し共感し合ったりするための、重要なコミュニティ空間として機能しているのです。企業からの公式な情報よりも、信頼するインフルエンサーや友人からの口コミ、あるいはSNS上で自然発生的に広がるユーモラスな表現(ミームなど)に心を動かされることも少なくありません。
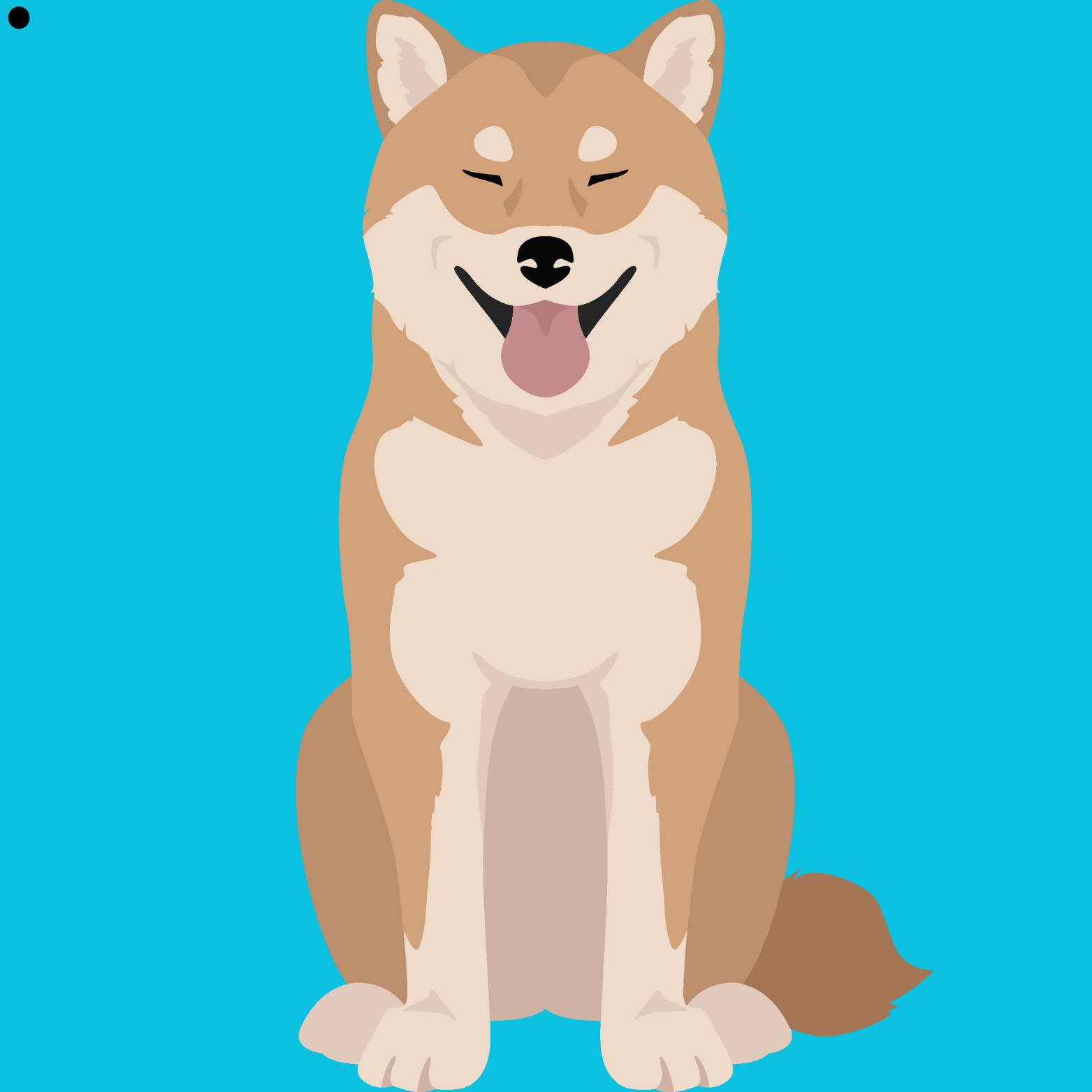
こうしたZ世代の新しい消費行動は、企業や、彼らを理解しようとする上の世代に、新たな視点をもたらします。
企業がZ世代の心を掴むためには、もはや製品の機能や利便性をアピールするだけでは不十分です。彼らが共感できるようなストーリーを語り、ブランドが持つ独自の世界観を丁寧に伝え、時にはファン同士が交流できるような場を提供するなど、感情的な繋がりを深めるアプローチが求められます。また、企業姿勢としての誠実さや透明性も、情報に敏感な彼らの信頼を得るためには不可欠な要素となるでしょう。
一方で、親世代にとっては、子どもの「推し」への熱中や、「エモい」という理由での買い物は、時に理解しがたい「無駄遣い」のように見えるかもしれません。
しかし、彼らにとってそれは、単なる浪費ではなく、自己肯定感を満たし、他者との繋がりを確認し、不安定な社会の中で心の拠り所を見つけるための、切実で重要な行為である可能性があります。その消費の裏にある価値観や感情に目を向け、一方的に否定するのではなく、なぜそれに惹かれるのかを理解しようと努める姿勢が、世代間の良好な関係を築く上で大切になるのではないでしょうか。
まとめ:Z世代こそ購買に情緒を重視する。
結論として、Z世代の「推し消費」や「エモ買い」は、従来の経済合理性だけでは測れない、人間の感情や共感といった根源的な欲求が色濃く反映された、新しい時代の消費の形を示しています。それは、単にモノやサービスを消費するだけでなく、それを通じて得られる体験、感情、そして他者との繋がりといった、より人間的な価値を重視する現代的な価値観の表れと言えます。
この新しい潮流を深く理解することは、企業が変化の激しい市場で未来を切り拓くためだけでなく、私たちが多様化する社会の中で他者を理解し、共に生きていく上でも、非常に重要な示唆を与えてくれるはずです。